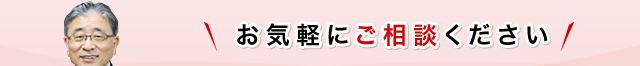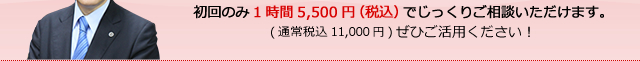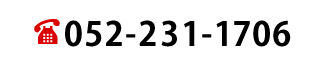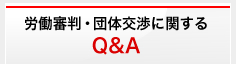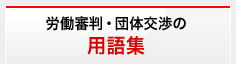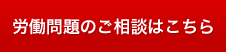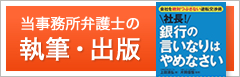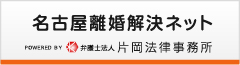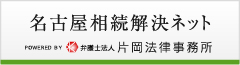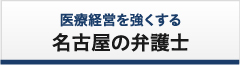経営法務
変更した就業規則が有効でないことがあるのですか?
これらの制度は、10年前に就業規則を変更して正式に導入したのですが、15年前から働いているある従業員Xさんが突然残業代を請求してきました。
就業規則に従えば、残業代は一切支払う必要が無いのですが、Xさんは現在の就業規則は無効だから、多額の残業代が発生すると主張しています。
変更した就業規則が有効でないことがあるのですか。
1 就業規則を変更する場合の注意点
労働条件を変更するために就業規則を変更することがありますが、きちんとした手続をとらないと変更後の就業規則が有効とならないことがあります。
まず、①労働者にとって有利な就業規則の変更は有効です。労働者に不利益は無いからです。
また、②労働者にとって不利益でも、適用を受ける労働者が個々に同意している場合も有効です。同意していれば無効としなくても良いだろうということです。但し、労働者が自由な意思に基づいて同意をし、そのことが客観的に明らかといえる同意書を取得することが必要であり、具体的にどのような不利益を受けるのか丁寧な説明をし、労働者が納得して同意したことを証拠として残す必要があります。
③労働者にとって不利益で、同意も無い場合でも、その変更が合理的であれば、有効になる場合がありますが、労働者の不利益の程度、労働条件の変更の必要性・相当性、労働者側との交渉経緯、等を総合的に判断するので、とても難しいです。
今回の事案ですと、変形労働時間制や固定残業代制を導入することで、労働者が不利益を受けるか、受けるとして、ちゃんと同意をとったか、あるいは変更の合理性があったか、が大事です。
手続がいい加減だと、変更後の就業規則が無効になることもあります。
2 規則を周知しましたか?
仮に就業規則の変更が許される内容であったとしても、それを従業員に周知していないと効力がありません。
周知していなかったために、就業規則の効力が否定され、敗訴した事案も多数あります。
したがって、従業員への周知は不可欠です。
たとえば、メールで全従業員に配布する、就業規則を誰でも見られる場所に置いて、その場所を知らせる、などの措置をとり、その旨の証拠を残す必要があります。
3 従業員代表の意見聴取
就業規則の中でも変形労働制をとるときなどは、従業員代表との労使協定が必要であったりします。
このような場合、適当に従業員代表を決めてしまっていると、無効になる場合があります。
民主的な方法(例:従業員が挙手で多数決をとる等)で決めていないために、変形労働時間制が否定された裁判例もあります(大阪地裁令和2年12月17日判決)。
よって、従業員代表を民主的に決めた過程も証拠に残すなどするべきでしょう。
4 結論
今回のご相談に即して言うと、就業規則の変更時に新規則の合理性の検討や同意書の取得、周知手続、従業員代表の適切な選出があれば有効ですが、いい加減だと無効になる可能性があります。生兵法は怪我のもとであり、社労士さんにも相談してしっかりと変更の手続を行いましょう。
月刊東海財界2025年2月号掲載
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
「経営法務」カテゴリーの他の質問はこちら
- 経歴書のウソを暴く(大学や前職に対しての弁護士会照会など)
- まだそんな身元保証書ひな形を使ってるんですか?無効ですよ。
- 著しい能力不足を理由として退職勧奨・解雇する方法は?
- 理不尽な残業代請求をされない方法は?
- フリーランス新法に対応するため何をするべきですか?
- 取引先からのハラスメント、無策はダメ
- 取引先が代金債権を譲渡してしまったが、納得できません
- パワーハラスメント対策では具体的に何をしたらよいですか?-1
- メンタルの不調を抱えた従業員への対応
- パワーハラスメント対策では具体的に何をしたらよいですか?-2
- パワハラについてわかりやすく教えてください
- 優秀な人材になるべく退職させないための制度の良し悪しについて
- パートタイム労働者などの待遇が正社員より悪い場合、働き方改革に関連してどのような対策が必要ですか?