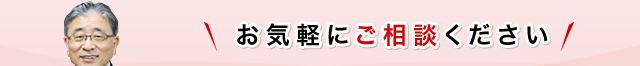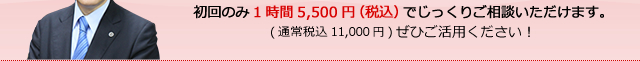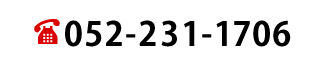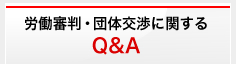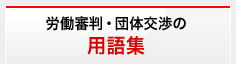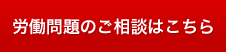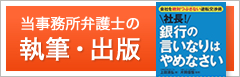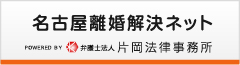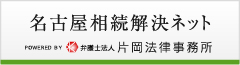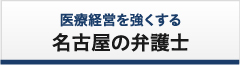経営法務
パワーハラスメント対策では具体的に何をしたらよいですか?-1
当社としても、人手不足が慢性化しており、パワハラで従業員が退職するのも困るため、必要な対策はとっておきたいです。具体的に何をしたらいいか、教えて下さい。
1 令和4年4月1日からパワハラ防止措置が義務化
令和4年4月1日から全企業にパワハラ防止措置が義務化されています。しかし、罰則が無いため、対策をしていない企業も多いです。
何も対策していないと、厚生労働省から指導・勧告を受けたり、社名公表等の不利益を受けますし、何よりパワハラを未然に防げません。
今回は、具体的にパワハラ防止措置として「何をしたらいいの?」ということで、すぐできそうな項目を説明します。
2 結局、何をしたらいいのか?
防止措置は全部で10項目あります。多いですが、簡単に実行できるものもあるので、できるところからやっていきましょう。
①会社として、パワハラを許さない!を全従業員に周知する。
パワハラが発生したら厳正に対処する!という会社の立場を明確にし、従業員に周知します。
周知のための文例は「パワーハラスメント対策導入マニュアル第4版」p59(厚労省HPを検索。)に載っていますので、これを活用して全従業員にメールや掲示等で周知します。
②相談窓口を設置する
パワハラを相談できる窓口を設置します。ごく小さい会社なら担当者は社長でもやむを得ないですが、事務長、人事・法務担当者、場合によっては外部の弁護士等に窓口になってもらいます。窓口について、窓口先、時間、担当者名、連絡先、相談方法等、を周知させます。
窓口担当者は、プライバシー等配慮するべきこともあるため、厚労省HP「あかるい職場応援団」等で研修させましょう。
③相談を理由に不利益な取扱いをしないことを定める
従業員に安心して相談してもらうために、「相談をしても不利益な取扱いをされることはないこと」を明確に規定し、従業員に周知することが必要です(③)。
以上、①②③の周知は、メールや掲示でまとめて行えばすぐできます。
④パワハラ防止研修を実施する。
従業員のパワハラに関する理解を深めるために、パワハラに関する研修を実施することも必要です。
独自に専門家に依頼して研修を行うことが理想的ですが、お手軽にやろうとすれば、厚生労働省が公開している動画やテキストを活用するのが楽です。一例ですが「あかるい職場応援団」等のHPを活用すると良いでしょう。
⑤就業規則等にパワハラの禁止とパワハラをした場合の懲戒規定を明記する。
パワハラをしてはいけないこと、どのような行為がパワハラに該当するか、パワハラをした場合は懲戒処分の対象となること、処分の内容の記載が必要です。
社労士さんに就業規則を修正してもらうか、自分で修正するなら、厚労省HPの「ハラスメント防止に関する就業規則規定例(パワハラ入)」をそのまま導入すれば良いでしょう。
その他、パワハラが発生した後の処理について、⑥パワハラが発生したら迅速かつ正確に事実確認を行う、⑦当事者のプライバシーを保護する、⑧被害者への適切なフォローを行う、⑨必要に応じて加害者に対する懲戒処分等を行う、⑩再発防止のための対策を行う、等がありますが、紙幅の都合上、次回にご説明したいと思います。
「パワーハラスメント対策では具体的に何をしたらよいですか?-2」へつづく
月刊東海財界2024年7月号掲載
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
「経営法務」カテゴリーの他の質問はこちら
- 経歴書のウソを暴く(大学や前職に対しての弁護士会照会など)
- まだそんな身元保証書ひな形を使ってるんですか?無効ですよ。
- 著しい能力不足を理由として退職勧奨・解雇する方法は?
- 理不尽な残業代請求をされない方法は?
- フリーランス新法に対応するため何をするべきですか?
- 取引先からのハラスメント、無策はダメ
- 取引先が代金債権を譲渡してしまったが、納得できません
- 変更した就業規則が有効でないことがあるのですか?
- メンタルの不調を抱えた従業員への対応
- パワーハラスメント対策では具体的に何をしたらよいですか?-2
- パワハラについてわかりやすく教えてください
- 優秀な人材になるべく退職させないための制度の良し悪しについて
- パートタイム労働者などの待遇が正社員より悪い場合、働き方改革に関連してどのような対策が必要ですか?