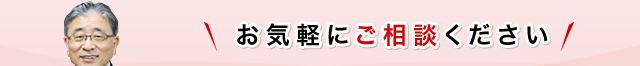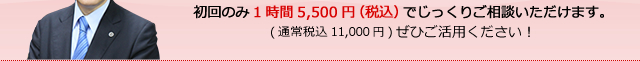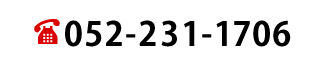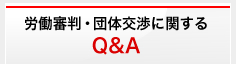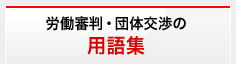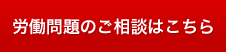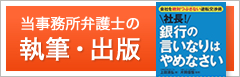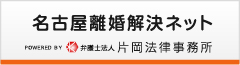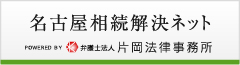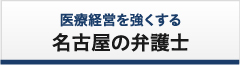経営法務
パワハラについてわかりやすく教えてください
管理職も、部下を指導するときに「パワハラに当たらないか?」と萎縮してしまい、指導に及び腰になるなど、社内で混乱が生じています。
パワハラを分かりやすく教えて頂けませんか?
1 パワハラの定義
パワーハラスメントという言葉は昨今よく耳にします。しかし、その中身を正確に知っている方は少ないです。
パワハラの定義は、改正労働施策総合推進法第30条の2第1項にあります。規定によりますと、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり、③労働者の就業環境が害されるもの(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)、という3要件から成ります。裁判例でも、これと同じ定義をしている例が多いです。
さて、「①優越的な関係」とは、職場の上司や、同僚・部下でも知識・経験が豊富で協力を得られないと支障のある等抵抗・拒絶しにくい者との関係を指します。
「②業務上必要かつ相当な範囲を超えた」というのは、業務上明らかに必要性がなかったり、業務目的を大きく逸脱していたり、業務遂行の手段として不適当であるような言動が当たります。
「③労働者の就業環境が害される」というのは、当該言動により労働者が身体的・精神的苦痛を受け、就業環境が不快なものとなり、能力発揮に重大な悪影響を受ける場合が当たります。
以上、ざっくり言うとパワハラとは、優位にある者から、業務の適正範囲を超えた、労働意欲を削ぐ身体的・精神的攻撃を受けること、と理解すればよいと思います。
2 何がパワハラに当たるのか(具体例)
以上のように法律・裁判例ではパワハラが定義されていますが、いかなる行為がパワハラに該当すると言われているのでしょうか。
一般的には、①身体的な攻撃(暴行・傷害)、②精神的な攻撃(脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言)が挙げられます。
さらに、③隔離、仲間外し、無視などの「人間関係からの切り離し」、④業務上明らかに不要なことや不可能なことの強制などの「過大な要求」、逆に、⑤程度の低い仕事を命じたり仕事を与えないなどの「過小な要求」、⑥私的なことに過度に立ち入ることもパワハラに当たります。
これらがパワハラに該当するのは、業務上の必要性がないか、必要性があったとしても相当性を欠く行き過ぎた行為と評価できるからです。
3 平常から注意すること
身体的な攻撃がパワハラに当たることは誰でも分かることだと思います。
難しいのは、言葉や態度による精神的な攻撃です。
その言動が、業務目的で必要性があり、業務目的のため相当な範囲であれば、パワハラには当たりませんから(1の②の要件)、ご自分や部下の言動が、業務目的のために必要か、その目的を達成するために穏当な内容となっているか、を日常的に意識するようにしてください。
そうすればパワハラだと批判を受けることもないはずです。
月刊東海財界2024年6月号掲載
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
「経営法務」カテゴリーの他の質問はこちら
- 経歴書のウソを暴く(大学や前職に対しての弁護士会照会など)
- まだそんな身元保証書ひな形を使ってるんですか?無効ですよ。
- 著しい能力不足を理由として退職勧奨・解雇する方法は?
- 理不尽な残業代請求をされない方法は?
- フリーランス新法に対応するため何をするべきですか?
- 取引先からのハラスメント、無策はダメ
- 取引先が代金債権を譲渡してしまったが、納得できません
- パワーハラスメント対策では具体的に何をしたらよいですか?-1
- 変更した就業規則が有効でないことがあるのですか?
- メンタルの不調を抱えた従業員への対応
- パワーハラスメント対策では具体的に何をしたらよいですか?-2
- 優秀な人材になるべく退職させないための制度の良し悪しについて
- パートタイム労働者などの待遇が正社員より悪い場合、働き方改革に関連してどのような対策が必要ですか?