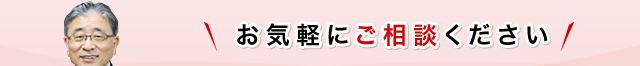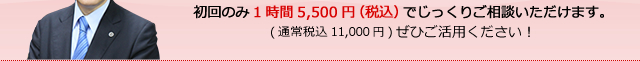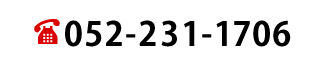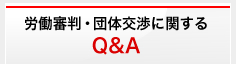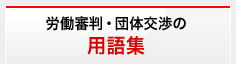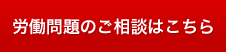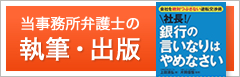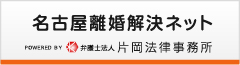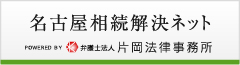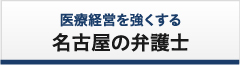経営法務
パワーハラスメント対策では具体的に何をしたらよいですか?-2
1 令和4年4月1日からパワハラ防止措置が義務化
前回ご説明したとおり、令和4年4月1日から規模を問わず全企業にパワハラ防止措置が義務づけられました。前回、全10項目ある防止措置のうち、5項目まで説明したので、残り5項目を説明したいと思います。
2 パワハラ防止措置というけど、結局、何をしたらいいのか?
前回説明した5項目は、パワハラが起きる「前」に準備しておくべき措置でした。例えば、パワハラを許さないという方針を従業員に周知する、とか、相談窓口を設置しておく、等です。
今回は、パワハラが現実に起きてしまった後の措置です。発生後に迅速に措置すれば、従業員に対する強い抑止力となり、将来のパワハラを防げます。具体的には、以下のとおりです。
⑥パワハラが発生したら、迅速かつ正確に、事実確認を行う
パワハラの相談があった場合は、被害者や加害者からの聞き取り調査を行い、速やかに事実確認をして下さい。調査をせず放置すると、そのことを問題視されてしまいます。
なお、注意してほしいのは、調査に当たって、加害者や第三者に聞き取りをすることを被害者に了解を取っておくことです。被害者の中には、周囲にパワハラ被害を知られたくない方もいて、そのような気持ちは尊重する必要があります。
事実確認は、加害者と被害者との言い分の食い違いを確認し、客観的な証拠の有無・内容、証人の有無・供述内容などを踏まえ、慎重に進める必要があります。
このような事実確認は、素人の方にはとても難しいかもしれません。どうしても企業内でできない場合は、迷わず弁護士などの外部専門家に相談して頂きたいところです。
⑦当事者のプライバシーを保護する
相談時や聞き取り等において、被害者や加害者のプライバシーを保護するために、十分な注意を払います。
関係者の聴取内容を企業がみだりに外部に漏らさないのはもちろんですが、関係者自身にも口外をしないよう指示します。
⑧被害者への適切なフォローを行う
パワハラが認められたときは、被害者と加害者を引き離すために配置転換したり、加害者へ注意や指導を行ったり、加害者から被害者に謝罪させたり、被害者へのフォローを行う等、適切なフォローを行って下さい。
⑨必要に応じて加害者に対する懲戒処分等を行う
パワハラが認められたときに加害者に何らの措置もとらなければ、加害者や周囲の人間が、会社の態度を見透かし、パワハラの再発が防げません。
よって、事実が認められた場合は、過去の例を踏まえつつ、厳正に懲戒処分を行うなど適切な対応をして下さい。
⑩再発防止のための対策を行う
個別の当事者への指導・懲罰だけではなく、パワハラの原因を探り、それを社内研修などで共有し(但し、プライバシーには配慮して下さい。)、再発防止に向けた対策をとって下さい。
以上、全10項目を説明しましたが、⑥以外はそこまで難しくはありません。できる限り積極的に措置を導入されますよう、読者の皆様もご検討になって下さい。
月刊東海財界2024年8月号掲載
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
「経営法務」カテゴリーの他の質問はこちら
- 経歴書のウソを暴く(大学や前職に対しての弁護士会照会など)
- まだそんな身元保証書ひな形を使ってるんですか?無効ですよ。
- 著しい能力不足を理由として退職勧奨・解雇する方法は?
- 理不尽な残業代請求をされない方法は?
- フリーランス新法に対応するため何をするべきですか?
- 取引先からのハラスメント、無策はダメ
- 取引先が代金債権を譲渡してしまったが、納得できません
- パワーハラスメント対策では具体的に何をしたらよいですか?-1
- 変更した就業規則が有効でないことがあるのですか?
- メンタルの不調を抱えた従業員への対応
- パワハラについてわかりやすく教えてください
- 優秀な人材になるべく退職させないための制度の良し悪しについて
- パートタイム労働者などの待遇が正社員より悪い場合、働き方改革に関連してどのような対策が必要ですか?